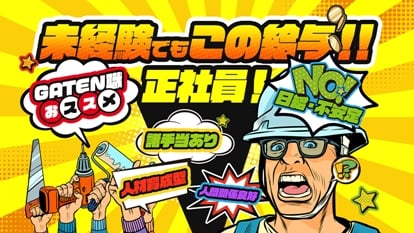「転職は通常、大卒がおこなうもの。高卒には難しいよ」
高校を卒業してから就職し、転職活動を始めた際、あなたが転職を考えていることを話すと、厳しい言葉が返ってきたことはありませんか?
求人サイトや各企業の募集要項に記載されている応募資格を見ると、学歴欄が「大卒以上」となっているものが多いですよね。
実際、高卒の転職は厳しいのでしょうか。
本記事では、高卒を対象とした求人数の実態や、大卒との平均年収の差やオススメの職種を紹介します!
「高卒だから転職は無理か・・・」と諦めず読んでください!
高卒にオススメの転職先は?高卒向けのお仕事とオススメの転職エージェント
高卒の転職は難しい?
世間では、「高卒の転職は厳しいよ」と噂が飛び交っています。
結論から言うと、高卒者でも転職は可能です。
正社員率や求人数をもとに、根拠を説明しますね!
30代高卒でも転職はできる!転職成功の方法とオススメの転職エージェント
高卒も大卒同様、正社員になれている
高卒でも、正社員は可能です。
実際、厚生労働省が発表している「平成28年度賃金構造基本統計調査」に実態が記されています。
同調査は、賃金の実態を雇用形態・学歴別等の指標を知るため、同年6月分の賃金をもとにおこなったもの。
調査結果によると、高卒の正社員率は57.1%です。
バイト・派遣などの非正規は42.8%でした。
結果を見ると、過半数の人は高卒でも正社員での就職に成功しているとわかりますね。
正社員率は判明しましたが、求人数はどれくらい市場に出回っているのでしょうか?
高卒でも求人数は多い
「有効求人倍率」をご存知でしょうか?
「仕事を探している人1人に対し、どのくらいの仕事があるのか」を示した数値です。
同倍率も、厚生労働省が取りまとめています。
2020年度の高卒者を対象とした調査によると、求人倍率は2.08倍。
1人に対し、2つ以上の仕事があることを示しています。
同倍率が高いほど、「景気がよく、企業が採用活動を積極的におこなっている」状況を指します。
日頃から倍率が高いかどうかを目にし、経済情報をつかむようにしましょう。
面接などで「普段経済ニュースを見ています」と、学習意欲の高さをアピールできますよ!
高卒の転職が難しいと言われるワケ
平均年収から、大卒との格差がわかりましたが、高卒だと転職活動が難しい理由はほかにもあります。
転職をしていると判明することや、入社後学歴で判断され、不利益を被る場合が具体的に挙げられます。
厳しい事実もありますが、現実だと受け止めるしかありません。
具体的に紹介します。
学歴で応募資格から外れるから
企業の採用HPには、募集要項が書かれています。
初任給や勤務地・休日数といった、働き始めてからの待遇等が記されたものです。
募集要項には、応募資格も。
中途であれば、企業が応募者に求める経験やスキルがあるほか、学歴も記載されています。
学歴は、「大卒以上」となっていることが大半。
高卒だと、応募資格の時点で対象外となっています。
仮に経験やスキルがあっても、高卒の学歴を見られて書類選考に通過しない恐れも。
高卒だと、スタートにすら立てない現状があります。
就職できても学歴差別があるから
就職後も、高卒のレッテルが張られます。
例えば、待遇で大卒者と差をつけられることです。
大卒の初任給が23万円スタートとなっていた場合、高卒だと20万円から、といったイメージ。
初任給の時点で数万円の違いがつけられています。
募集職種も、総合職は大卒が対象となっており、事務職は高卒以上といったことも。
一般的に、総合職の方が事務職より年収は高い傾向にあります。
仕事内容の難易度や転勤の有無といった違いが生じるためです。
大卒者だからといって、必ずしもすべての仕事をそつなくこなせるわけではありません。
転勤も、人によっては拒絶する人も。
「高卒の自分ならできるのに・・・」と、大卒者と明確な差を働き始めてから感じ、理不尽さに憤ることもありますよね。
早期退職されると企業が懸念しているから
高卒だと、「すぐにやめてしまうのでは?」と企業側が懸念することも原因として挙げられます。
大卒者と比べ、4年早く社会に出た高卒。
大学に入学すると、勉強だけでなくサークル活動・バイトといった学校外や社会との接点を持てます。
社会を多少なりとも知っている大学生は、就職してからも社会の渦にくじけず頑張ってくれるはずだー。
企業が大卒者に抱く理想像ですね。
対して、高卒者は主に部活と勉強だけ。
バイトをする日があっても、学校の規則により日数や1日の労働時間が決められています。
「高校を出たばかりじゃ、社会のことをなにも知らない。つらいことがあったらすぐに逃げ出してしまいそう」と判断し、高卒者の採用を見送る企業もあります。
高卒転職の年収事情
上記で、高卒者の求人数や正社員の倍率を目にしてきました。
転職は、内定をもらったらゴールではありません。
次に働く会社から、どれほどの給与をもらえるのか気になりますよね。
一人暮らしなら、家賃をはじめ食費や光熱費といった生活費がかかります。
実家暮らしでも、親に収入を渡す家庭もありますよね。
自分がもらう年収は、ほかの高卒者と比べ多いか少ないかー。
高卒者の平均年収や、大卒者との差を見ていきましょう。
高卒者の平均年収
まず、高卒者の平均年収です。
厚生労働省が2019年6月分を対象におこなった「令和元年賃金構造基本統計調査」に、学歴別の平均年収が記されています。
同調査の結果によると、高卒者の全世代平均年収は292万9000円。
最も低いと、19歳までの世代で182万7000円です。
最多は、55~59歳で349万1000円となっており、世代間格差は最大で167万円あります。
20~24歳になると、平均年収は203万円。
20歳を過ぎると、平均で20万円ほどアップしています。
年齢はひとつのボーダーラインと言えますね。
60歳以上を過ぎると、平均年収はガクンと落ちて259万7000円台に。
定年退職を迎え、正社員であっても給与が下がったり、非正規で働く可能性が考えられます。
大卒との年収差はどれくらい?
高卒者の平均年収は上記で見ましたが、大卒者の年収はどれくらいでしょうか。
高卒の平均年収で見た同調査には、大卒者の平均年収も記されています。
大卒の場合、卒業するのは浪人・留年等がなければ22歳。
20~24歳の世代が該当し、229万2000円台となっています。
高卒の同世代と比べ26万円の差がありますね。
最も高いと、55~59歳で522万9000円。
高卒の同世代と比べ173万年の差があります。
55~59歳だと、家族を持っている方なら子供が大学・専門学校等に進学したり、就職している世代。
教育費を払う際、親の年収が高いほど充実した教育を受けさせられます。
同世代における、高卒と大卒の平均年収の差173万円は、私立大学なら学費1年以上分に該当。
高卒と大卒には、大きな壁が存在しているのは確かです。
高卒でも転職して高収入を狙える?高収入を目指せる転職先を紹介
企業が高卒転職者に抱く懸念点
高卒者の転職が厳しいと言われる理由には、上記のような大卒者との違いが挙げられます。
ほかにも、大学に進学しなかった事実をもとに、評価が下がるポイントが。
実際にどういったものがあるのか見ていきましょう。
学習意欲や能力の低さ
ひとつには、学習意欲や能力の低さがあります。
大学受験をしなかった場合、受験に向けた勉強をしていません。
高校まで習った学習内容をどれほどインプットできて、アウトプットにつながるかー。
日々の学習意欲と能力が求められますよね。
高卒だと、受験に向けた学習をしていなかったので、「仕事を覚える気はあるんだろうか」「どれくらいで仕事に慣れてくれるんだろうか、仕事内容を理解できるのか」と企業側が疑問を抱きます。
大学受験をしなかっただけですが、「学習意欲や能力が低い」と思われている可能性があります。
努力を続けられるか
継続して努力してくれるかどうかも見られます。
大学生の場合、まずは大学受験に向けて勉強していたことを評価されます。
一般・推薦等の入試形式による違いはありますが、いずれも対策が必要です。
合格に向けて多少なりとも努力はしていたので、大卒者は頑張りの点を評価されます。
入学後も、バイトやサークル活動に励んでいたことも、いい印象を与えられますよね。
対して、高卒だと大学受験はしていません。
「勉強を途中でやめた」と思われます。
高校生は部活動に所属するのが原則ですが、顧問の指示のもと活動するのが一般的。
自主的に動いていたよりも、いかに上からの判断に従えたかが重要となります。
努力は関係なく、言われたことをやるだけ。
部活経験者だけの高卒に対するイメージはよくありませんね。
高卒未経験でも転職できる業界
「高卒だと、転職はできないのか」と心が折れてしまいそうですが、あきらめないでください。
高卒でも、未経験の応募が可能な業界があります。
いずれも、学歴よりも人柄や入社後の頑張りに将来性があると判断されれば、採用や選考通過につながる可能性にみちた業界です。
ひとつずつ見ていきましょう。
IT業界
IT業界は近年、業界の拡大を続けています。
ITを駆使した業務効率化がどの企業でも進んでいるためです。
ベンチャー企業だったIT企業が、社会で高まる需要に応えて上場できるほど、ITのニーズは高まっています。
2020年から始まった、新型コロナウイルスの感染拡大もきっかけのひとつ。
人同士の接触を避けるため、各企業はテレワークや在宅勤務の導入を開始。
従来、国内企業は社員を出社させて対面方式で仕事をしてきました。
コロナは、多数の人が同一空間にいると感染しやすくなると報道されています。
テレワークはいわゆる「密」状態を回避し、感染リスクを抑えるための施策。
オンラインを使って仕事ができるよう、各種システムの導入や開発が相次いでいます。
コロナの終息が見通せない中、今後もIT業界の仕事のニーズは増すばかり。
人材不足から、未経験でも育てていく企業もあるので注目の業界ですね。
飲食業界
飲食業界も、人手不足が著しい業界の一つ。
レストランや喫茶店、居酒屋・ラーメン屋・・・。
提供するメニューに差はありますが、幾多のお店が展開しています。
必要となるスタッフも多岐にわたります。
お客の注文を聞いて厨房係に伝えるホール、ホールから受けた注文内容をもとに1分でも早く料理するキッチン。
会計をしたいお客に対応するレジ係や、店を経営する店長などが挙げられます。
日々、人気のグルメは変化を見せています。
タピオカは数十年前にも小さなブームを見せていましたが、ここ数年間は爆発的ヒット商品となりましたよね?
トレンドの移り変わりは激しいですが、人気を抑えれば一獲千金の夢が広がる業界。
新規オープンが相次いでいることから、飲食業の人手は今後も増していく可能性がありますね。
運輸業界
運輸業界も未経験からチャレンジできる業界です。
近年、ネットショッピングの台頭に伴い、届ける荷物の数は激増中。
実際、国土交通省がおこなった調査によると、2019年度の宅配便の合計数は43億2300万。
3年前と比べ6億個も増加しています。
日本の総人口は1億人程度なので、人口の数十倍の荷物数が日々送られています。
年間で43億個もあると、大変なのは届ける人の数。
具体的には、ドライバーのことです。
1日でさばく荷物量が多すぎて、連日休憩時間を削ったり長時間労働が問題視されています。
人手不足に悩む業界ですが、ポジティブに考えられる要素もあります。
各方面に向けて車を走らせるため、「いろんな場所に行きたい」「運転するのが好きだ」と考える方には適した職種ですね!
製造業界
高卒から製造業界に目指せます。
具体的には、工場勤務ですね。
食品や印刷など、一言に工場と言っても業種は様々。
どの工場も、日勤・夜勤制のシフトを導入し、人員を動かしています。
食品工場なら、コンビニや製パンメーカーの工場が挙げられます。
日々、コンビニで陳列されているお弁当やおにぎり・菓子パンの製造工程を間近で関われる仕事。
お弁当がどのようにできているのかがわかります。
廃棄寸前や余った食品を持ち帰ってもよいとする工場もあるので、食べたい人には天国の環境ですね!
弁護士・税理士業界
「弁護士」「税理士」と聞くと、大卒の中でも上位大学でないと難しいイメージがありますよね?
高卒からでも、目指せるルートはあります。
弁護士になるには、司法試験の合格が必須。
司法試験は、誰でも受験できるものではありません。
法科大学院を卒業するか、司法試験予備試験に合格する必要があります。
法科大学院は弁護士・検察官・裁判官を志す人を対象とした大学院。
入学するには大学を卒業しなくてはなりません。
高卒の方が目指すは、司法試験予備試験の合格。
同試験は、本番の司法試験と出題内容が似ており、勉強することで司法試験対策にもなります。
予備試験への合格で、法科大学院を卒業した人と同じくらいの学力があると証明でき、司法試験の受験資格を得られます。
税理士も、税理士試験に合格することで就ける職業。
応募資格は、大学等で法律や経済を学ぶ学歴もありますが、資格や職歴でアピールすることで得られます。
高卒の場合、司法試験か公認会計士の試験合格か、簿記の上級資格取得。
資格のほかにも、会計事務所で2年以上の実務経験があれば受験資格をゲットできます。
いずれも、本番の受験資格を得ただけなので、試験に合格したのではないことは留意しましょう。
難易度が高い試験のため、勉強は必須。
死に物狂いで勉強しましょう!
高卒未経験でも目指せる職種
上記では、業界を指標に高卒未経験者でも目指せる業界を見ていきました。
具体的には、どのような職種があるのでしょうか。
次からは、職種ごとに見ていきます!
営業職
営業職は学歴不問であることが多いです。
会社の利益・売り上げにダイレクトに貢献できる営業職は、結果を残すことがすべて。
学歴は関係ありません。
扱う商材の内容を理解し、顧客に説明できる能力は必要ですが、大事なのはいかにして売り込むか。
知能よりも、話し方や相手の懐に入っていけるかが重要となります。
話し上手なら、営業でもうまくいく可能性があります。
対して、控えめな人だと大卒であっても営業職で成果を上げるのは難しいです。
中高時代、クラスの盛り上げ役など周囲を巻き込む力がある方は、営業職を検討してください!
事務職
事務職は高卒の方が応募資格を満たせる職種。
経理・広報・総務など多岐にわたる職種に配属される可能性のある総合職は、大卒以上でないと厳しいですが、データ入力や社員補助といったサポートする仕事が一般的な事務職であれば学歴は関係ありません。
大手企業でも、高卒を対象とした事務職の募集があります。
大手なら安定した会社で、福利厚生や休日数など待遇の良さが挙げられます。
事務職を募集している大手企業という指標から求人を探すのもありですね!
接客・販売職
接客や販売職も学歴を不問としています。
上記で見たような、飲食店は接客業にあたります。
販売職は、例えば家電量販店で働く店員。
格安スマホや家電の説明をしている人たちですね。
販売員の場合、目の前にいるお客にいかにして「買いたい!」と思わせるかが大事となります。
単に商品の説明をするのでは、お客は聞く耳を持ちません。
どういったニーズがあって、来店してきているのか。
なにを探しているのか。
どういった値段なら買えるのか。
一例ですが、お客の懐に入るために聞き出す必要がありますね。
ガツガツした営業スタイルだと、お客は嫌がって買わなくなる恐れも。
お客の反応を見つつ、適度なバランスが必要ですね!
公務員
公務員になるには、公務員試験への合格がマスト。
大卒者を対象とした職種以外にも、高卒で受験できる職種もあります。
高校の進路相談課や進路実績を見ると、「公務員試験対策!」と書かれたポスターを目にしたことはありませんか?
高校内で掲示されているので、高卒を対象とした職種があることがわかりますね。
公務員の職場は、各市町村の役場といった地方行政から、省庁といった国家行政も。
例えば、外務省も高卒に門戸を開いた職種があります。
大卒の方を対象とした職種の補佐的な仕事が多いですが、海外勤務も可能。
高卒の方でもエリートになれますね!
プログラマー
プログラマーは近年、IT業界の需要増加に伴い人材不足が叫ばれています。
勉強した分だけできることが増え、仕事の成果につながりやすいプログラマー。
大卒でなくても、資格や勉強を積み重ねれば就ける職業です。
近年、流行を見せている新型コロナウイルス感染拡大に伴うテレワークの普及で、今後ますますプログラマーの仕事の幅が広まる可能性が高いです。
学歴を気にせず、勉強意欲をアピールしましょう!
施工管理職
施工管理職とは、建設現場において工程・安全・品質管理をおこなう仕事です。
工事や予定されている建造物が大きくなったり長期案であるほど、工程数や種類は複雑さを抱えます。
技術者の数も増加するため、計画性と質の高い工事をおこないます。
発注者とのかかわりや技術者への指導といった、現場の管理や監督業務を任されます。
施工管理技士の資格があると、仕事の幅や待遇アップにつながりやすいので、資格取得はセットだと考えておきましょう。
高卒が転職活動をうまく進めるコツ
高卒でも対象となる業界や職種を見てきました。
いざ転職活動を開始するにあたり、いくつか事前に準備しておくことがあります。
転職活動を始めてからだと、迷いや知識・経験不足から「どうすればいいんだろう・・・」と考えが止まり、順調に進まなく恐れも。
どういった行動が必要になるのか、詳しく見ていきましょう!
高卒フリーターが正社員として就職する上で知っておきたい大切なポイント
興味のあること、嫌いなことを考える
転職活動を考える際、業界や職種から探す人もいますよね。
業界・職種を見る際、あなたはなにに興味があって、興味がない(嫌い)なのか考えてみましょう。
好きこそものの上手なれ。
好きなことには熱心になれるし、工夫を凝らして上達が早くなる、という意味のことわざです。
好きなことなら、仕事にやる気をもって挑めますし、長続きできますよね。
対して、関心のない仕事だと、日々つまらなくなります。
短期離職や転職回数が積み重なってしまうので、興味のある業界・職種や好きなことを仕事にできないか、熟慮する必要がありますね。
学歴不問の求人を探す
営業職・販売職といった職種で見たように、学歴不問の求人を探しましょう。
応募資格を目にし、「大卒以上」となった場合だと書類を提出してもあっさりと落ちてしまいます。
学歴不問の会社の場合、あなたと同じように最終学歴が高卒の人も働いています。
同じ高卒の人同士だと、なにか聞きたいことがあっても質問しやすいですし、仲良くなりやすいですよね!
学歴を重視しない会社がないか、調べてみましょう!
未経験可能の求人を探す
未経験でも募集している求人かどうかも大事なポイント。
興味があったり、やりたいと思った仕事があっても、経験者のみの募集だと応募資格から外れますよね。
経験がない場合、書類や面接で重視されるのは人柄や将来性。
年齢が若いほど、将来性があると判断されます。
人柄は、いかにして「一緒に働きたい」と思ってくれるか。
元気な声で受け答えするのはもちろん、「なにか質問ありますか?」と聞かれたら2~3個の質問を事前に考えましょう。
「入社後も積極的にわからないことを聞きに来てくれそうだ」
「学習意欲が高い」
「コミュニケーションを取りやすそうな人だ」
入社後の働くイメージを具体的に持ってもらい、人柄面で評価されるように努めましょう!
続けられそうな仕事かどうか考える
長く勤められる仕事・会社なのかどうかも考えましょう。
国内では、転職回数が多いと仕事をすぐに変える「ジョブホッパー」とみられ、転職活動をしても「1年以内にやめるのでは?」と企業側に疑念を持たれます。
ひとつの会社で働いた期間が長いほど、次に転職を検討したときに有利になる傾向が。
一般的に、3年以上は働くようにしましょう。
3年以上働けるかどうかは、仕事内容もですが会社の雰囲気も影響します。
残業を強いて残業時間が多かったり、離職率の高い企業は長く働ける環境にありません。
ネットなどで企業や仕事に対する口コミが上がっているので、できる範囲で調べておきましょう!
エンジニアはオススメの職種
IT業界のうち、エンジニアはオススメ度が高い職種です。
どの業界・会社でも、PCを駆使した技術職やエンジニアの人はいます。
会社のサイト構築や、経理といった事務作業を効率よく進めるために必要な仕事だからです。
未経験でも入社できれば、勉強量や経験業務を積み重ねれば、一流のエンジニアになれる可能性が。
職種のニーズ増加に伴い、結果を出せば高待遇も得られるので、エンジニア職も視野に入れた転職活動をしてみましょう!
資格を取る
高卒で転職を成功させたい場合には、資格を取るのがおすすめです。
高卒でも資格を取ることによって、学歴以上に転職に役立ちます。
また即戦力としても認めてもらえる可能性が高まるため、高収入を狙えます!
具体的におすすめの資格は以下の通りです。
- 宅地建物取引士
- MOS
- ITパスポート資格
- 日商簿記検定
- 登録販売者
- TOIEC
- 通関士
- 基本情報技術者
- 調理師免許
- 行政書士
これらの資格についての具体的な説明は下記記事でおこなっているので、ぜひ参考にしてくださいね。
高卒の転職は資格があると有利になる?おすすめの資格10選を徹底解説!
転職サイト・転職エージェントを利用する
高卒で転職を成功させるのであれば、キャリアアドバイザーにサポートしてもらうのが一番です。
転職エージェントを利用すれば、キャリアアドバイザーにサポートしてもらえるので高卒の方でも安心して利用できます。
具体的におすすめの転職サイト・転職エージェントは以下の通りです。
- ハタラクティブ
- DYM就職
- doda
それぞれ解説します。
高卒におすすめの転職サイト・転職エージェント!選び方や利用するコツも解説
ハタラクティブ

- ハタラクティブの特徴未経験や経歴に自信がない方に特化している
- 20代の転職をサポートしてくれる
- LINEでも連絡が取れるから便利
- 安定した企業への紹介も多い
ハタラクティブは、20代のフリーターやニート、中卒や高卒の方におすすめの転職サービスです。
未経験や経歴に自信がない方を中心に転職サポートをしているので、高卒者に非常におすすめ!
キャリアアドバイザーとのカウンセリングではしっかりと希望を聞いてくれるので、安心して利用できますよ。
またラインで相談することもできるので、非常に便利です!
ほかの転職サービスだと、専用のチャットツールを利用しなければいけないこともあるので、面倒に感じるかもしれません。
ハタラクティブであれば、日常的に使っているツールで連絡を取れるので簡単ですね!
またハタラクティブを利用するのに料金は一切かからないので、安心して利用してみてください。
\未経験・無資格OK!/
DYM就職

- DYM就職の特徴第二新卒やフリーターに強い
- 転職できるまでサポートがある
- 自分に合った求人が分かる
- 内定後の退職や入社の手続きも任せられる
DYM就職フリーターやニート、中卒や高卒などの転職支援をしているサービスです。
DYM就職には書類選考ナシで面接できる求人も掲載されているので、高卒で経歴に自信がない方にもおすすめ!
キャリアアドバイザーにサポートしてもらいつつ、転職を効率的に進めたい方はぜひ利用してみてくださいね。
もちろん費用は一切かからないので、とりあえず登録してみるのもおすすめです。
とりあえず転職の相談だけでも問題ないので、ぜひ登録してみましょう!
\3分で登録完了!/
doda

| 求人数 | 約260,000件 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国47都道府県 |
| 料金 | 無料 |
| 公式サイト | https://doda.jp/ |
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
- dodaの特徴自分に合った方法で求人を探せる
- 転職に不安がある方も忙しい方も安心のサポート
- 転職活動に関するコンテンツが充実している
- エージェントやスカウトサービスも利用できる
dodaは掲載されている求人数が10万件以上もあるので、非常に多い選択肢の中から希望する求人を見つけられます。
またdodaは転職サイトと転職エージェントのどちらとしても使えるので、自分で求人を探したい方やキャリアアドバイザーに探してもらいたい方の両方におすすめ。
高卒として初めての転職の場合、不安なことも多いはずなのでキャリアアドバイザーにサポートしてもらえるのはありがたいですね!
dodaにはスカウト機能も用意されており、自分で求人を探さなくても転職活動が進むので効率的です。
高卒の転職コラムや悩みの解決方法についても調べられるので、ぜひ利用してみてくださいね。
\最短60秒で登録完了!/
高卒の転職希望者が面接で気を付けること
上記で、高卒にオススメの職種や業種を説明しました。
書類選考を通過すれば、面接が待ち構えています。
面接時に、どういったことを聞かれ、意識すべきことはなにか。
話す内容が大事になるので、心掛けましょう!
具体的に見ていきます。
学歴重視はまだまだ多いことを認識する
学歴不問の会社があるとはいえ、日本の企業は学歴社会だと忘れないようにしましょう。
面接まで呼ばれたなら、高卒にも社員募集の門戸が開かれている証拠。
「もう内定もらえる!」と安心するのは時期尚早です。
「あなたは高卒なので、まずは簡単な仕事から始めてもらいます」と、学歴を理由に仕事内容に差をつけられることを言われる可能性が。
入社後も学歴で判断されることがあることを頭の片隅に入れておくと、入社後のギャップを最小限にとどめられますね。
大学に進学しなかった理由をポジティブに説明する
前段落で説明したように、国内企業は大卒を重視する傾向にあります。
面接でも、学歴を気にする企業から質問される場合があります。
「なんで大学に進学しなかったの?」
「大学受験はあきらめたの?」
「勉強はどれくらいできるの?」
大学に行かなかった理由が家庭の事情なら、まずは正直に伝えましょう。
「家庭の事情で、経済的に大学に進学できませんでした。『大学の学費を払えない』と親から言われたとき、『自分が家族を支えていこう』と決意しました」
前向きであり、頼もしい一言ですよね?
「大学に行きたくなかった」「大学受験したくなかった」等のネガティブな理由は言わないように気を付けましょう。
高校時代までに頑張ったことを振り返る
「学生時代に頑張ったことを教えてください」
大学卒業見込み者が、新卒の就活をしていると、面接でよく聞かれる質問です。
大学生の場合、サークルや部活・研究等で学生生活を語れます。
高校で卒業した場合、部活や勉強面をアピールしましょう。
生徒会に所属していたなら、同会での活動がPRポイントに。
生徒会の活動内容は、「学校を今後どのように発展させていくか」を主な目的としています。
自主性が高く、後輩をまとめる能力も必要に。
考える・行動した経験を社会に出てからどのように活かせるのか考えておきましょう!
前職の退職・転職希望理由を前向きに伝える
「前の会社はなぜやめた(やめようと)のですか?転職活動の理由は?」
転職活動の面接だと、前職の退職理由や転職理由を聞かれます。
就業中なら、「やめようとしている理由」といった表現。
大学進学しなかった理由と同様、前向きなことがきっかけだと強調しましょう。
「前職では営業をしていました。結果に結びつくことがあり、商材説明がより難しくなる会社で働いてみたいと思います」
残業時間や営業の辛さといった理由が本音を伝えてしまうと、「ウチに入っても同じようなことを言ってすぐ退職するのでは」と、短期離職を懸念される恐れが。
明るく話しているかどうかも重要になるので、話し方も含め練習しましょう!
高卒が就職で勝ち組になれる理由!オススメの職種や仕事探しのコツも紹介!
高卒の転職で求人探しのコツ
高卒の方でも応募資格のある職種や、面接時に心掛けることなどを見てきました。
「求人を探すときは、どこで見たらいいの?」
「希望通りの求人がない・・・」
「相談したい場合は誰に聞いたら?」
求人を探す際、疑問が浮かびますよね。
疑問内容に沿った、利用先を紹介します!
求人サイトを利用する
転職をする際、一般的に求人サイトを利用する人が大半です。
勤務地や待遇・職種等の項目から、自分の希望に合った求人をしている会社を見つけられます。
例えば、マイナビやリクナビ・dodaなど、民間企業が運営しているサイト。
いずれも、個人情報の登録は必須になりますが、登録や利用は無料です。
希望条件に合致した求人で、新しく募集が始まった会社があればメールで通知する機能も。
全国各地・様々な職種が掲載されているので、自分に理想的な会社が見つかる可能性が高いです。
ぜひ利用しましょう!
ハローワークで相談する
ハローワークも一つの手です。
「無職や、中年以降でクビになった人が行くところじゃないの?」といったイメージがありますか?
実際は、大学生の新卒を対象とした求人も紹介するなど、若い人でも利用できます。
求人サイトに掲載されていない企業もあるので、掘り出し物の感覚で好条件の求人が見つかる可能性も。
利用に当たり、住んでいる地域が担当している最寄りのハローワークを確認し、登録の手続きをする必要があります。
実際に応募したい企業があっても、ハローワークから紹介状をもらう手間もありますが、求人サイトの利用より使いやすいと感じる人にはオススメですね。
高校の進路相談課に相談する
就職実績のある高校の場合、進路相談課に相談を持ち掛けるのもありです。
卒業した高校でも、仲が良かったり面倒見の良い先生なら、卒業生にも対応してくれます。
地元のことを知る先生しか知らない企業を紹介してくれることも。
書類の書き方や面接練習などにも応じてくれる場合、気軽に乗ってもらいましょう。
ハローワークや求人サイトといった、初対面の人とのやり取りだと緊張や人見知りを発揮する人は、高校の方が求人を探しやすくなりますね!
エージェントを利用する
エージェントの利用も一つの手段です。
求人サイトに登録すると、「エージェントを使ってみませんか?」等のお誘いを見たことはありませんか?
エージェントは、人材を募集している企業と仕事を探している求職者の間に立ち、両者の仲介をする仕事をしている人です。
求職者がエージェントに対し、待遇や職種等の希望条件を伝えます。
エージェントはもらった希望条件の情報をもとに、求職者の希望に近い求人の紹介をします。
自分で探すより手間が省け、企業側に「○○という人材がいますが、いかがでしょうか」といったように推薦をしてくれる場合も。
エージェントと関係性を構築しておくと、転職活動がうまくできます!
検討してください!
高卒におすすめの転職サイト・転職エージェント!選び方や利用するコツも解説
【まとめ】高卒転職はしっかりと行動すれば難しくない!
本記事では、転職を考えている高卒者に対する転職の実態や応募資格のある職種を説明しました。
実際に読んで、参考になった部分もありましたよね?
転職活動は、インプットだけでは不十分。
知った情報やコツを今日から活かすことが重要です。
希望条件ややりたい仕事ができるよう、積極的に動いて転職活動を成功してくださいね!