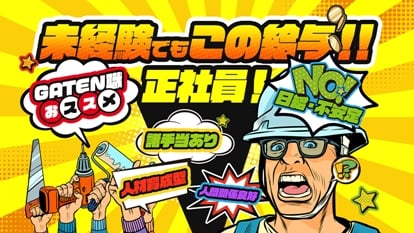第二新卒が転職を成功させるコツは?
厚生労働省の『平成30年若年者雇用実態調査の概況』によると、若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考で重視した点は「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」だと回答した割合がもっとも高いです。
前職でほとんど経験やスキルを身につけられなかった第二新卒でも、ポテンシャルを上手にアピールすれば、転職を成功させられます。
また、短期離職を繰り返さないために、自分にはどんな仕事が合っているのかじっくり考えることも大切です。
今回は、第二新卒が転職を成功させるコツを解説します。
- 第二新卒が転職を成功させるためには、時間をかけて自己分析するべき。譲れない条件を決めておくこと、企業側のニーズを調査することも大切。
- 求人数が多くなる時期は1月~3月、7月~9月。
一度でも就職していれば第二新卒者
これから転職活動を進める方の中には、第二新卒と新卒の違いについて今一つわからない方もいるかもしれません。
自分が第二新卒なのか新卒なのか判断できないときには、学校を卒業してから就職した経験があるかどうかを考えてみましょう。
第二新卒は「就職して1年から3年ほどで転職を考えて就活している人」
第二新卒は、「就職してから1年から3年ほどで転職を考えて就活している人」というのが一般的な考え方です。
したがって、就職してから3年未満の間に転職活動を始めた場合は、第二新卒として扱われる可能性が高くなるでしょう。
一度でも就職してから転職活動をしている20代も第二新卒
一度就職したものの1年未満で退職してしまい、新たに転職活動をしている20代も、第二新卒にあてはまると考えられています。
ただ、このように入社1年未満で転職活動を始める第二新卒は、いわば短期退職者や早期退職者に当たります。
短期退職者や早期退職者は企業から敬遠される傾向があるため、一度就職した実績があるにもかかわらず、応募できる求人の数が減ってしまう可能性があるので注意が必要です。
ほかの世代の転職者との違い
第二新卒には、ほかの世代の転職者と異なる点がいくつかあります。
転職市場における、第二新卒ならではの特徴をご紹介してみましょう。
専門的なスキルはさほど求められない
20代以外の転職者は、前職での業務経験を問われる傾向があります。
仕事をしていた期間が長くなるほど、このような業務経験はしっかりとチェックされます。
その点第二新卒は、職業経験があるといっても就業していた期間がかなり短く、専門的なスキルについてはさほど厳しくチェックされないケースが少なくありません。
以前の勤め先の社風、企業色に染まっていないことが多い
第二新卒のように1年から3年前後の就業であれば、以前の勤め先の社風や企業のカラーにも染まっていない可能性が高いです。
こういった人材は、スムーズに会社に馴染んでくれると期待できますので、企業側としても前向きに採用を検討したい人材になります。
ビジネスマナーと柔軟性が選考のポイントに
最低限のビジネスマナーと、若手としての柔軟性があるかどうかが、第二新卒の転職では重視されます。
即戦力としてのスキルがなくても、将来性があると判断してもらえれば、採用になる可能性があるでしょう。
第二新卒者が新卒者よりも有利な面
第二新卒は新卒とは異なり社会人経験がありますので、転職活動においてもプラスになることがあります。
社会人としてのスキルがある
第二新卒は、たとえ短期間でも職場で働いた経験があります。
新入社員研修などを受けていることも多く、基本的なビジネスマナーが身に付いているケースが少なくありません。
このような第二新卒は、企業側にとっても魅力的な人材です。
ビジネスマナーを1から教えなくて済むというメリットがあり、転職活動でも有利になりやすいと言えます。
前職で身につけた能力やスキルがアピールポイントになる
第二新卒の転職活動では、前職で身に付けた特定の能力、スキルなどが求められることがあります。
例えば、接客の仕事を経験した方であれば、コミュニケーション能力や接遇のマナーなどが身に付いているかどうかを選考の際にチェックされるわけです。
数カ月から数年程度、同じ仕事を続けていれば、だいたいは何らかの能力やスキルが身に付いていますので、転職活動でも堂々とアピールすることができます。
アピールポイントが得られるところは、第二新卒ならではのメリットと言えるでしょう。

新卒時の就活でおとされた企業で働けることも
第二新卒での転職活動においての良い点として、「新卒時の就活で不採用になってしまった企業で働ける可能性もある」という点も挙げられます。
社会人経験を経ることによって、新卒就活時には気づけなかった強みや長所が見つかったり、新たなスキルを習得したりしたことによって、新卒就活時に不採用となった企業のニーズに合致した人材に育っていることもあるのです。
一度は諦めかけた企業で働ける可能性が出てくることは、第二新卒者にとっては嬉しいですよね!
このように第二新卒者は、自分が得た経験やスキルを、憧れの企業で発揮するチャンスがあるのです。
内定直後にはたらける
第二新卒者が新卒者と比較して有利な点として見逃せないのが、「内定直後にはたらける」という点があります。
新卒就活者の場合、無事に企業から内定を獲得できたとしても、卒業までに期間があるために、すぐに働き始めることはできません。
一方第二新卒者の場合は既に学校を卒業しているため、内定さえ獲得できれば、間を空けることなくすぐに働くことができます。
内定直後から働くことができれば、早い段階から仕事に慣れることが出来るだけではなく、モチベーションが高い状態で仕事を始めることができますよね!
また人手不足の企業にとっても、内定後すぐに働いてくれる第二新卒者は心強い存在と言えるでしょう。
転職活動を行うときのデメリット
転職活動を行ううえでは、第二新卒ならではのデメリットもいくつかあります。
採用担当者から不安視されやすい
第二新卒は前職を短期間で辞めていることから、採用する側としても「すぐに退職してしまうのではないか」と不安になってしまう場合があります。
前職を辞めた理由を詳しく聞きたがる採用担当者も少なくなく、相手が納得できるような説明をすることが大切になるでしょう。
待遇が悪い場合がある
第二新卒の新入社員は、いわば中途採用の扱いになるケースが多いです。
中途採用者については、長く勤めてくれる新卒の人材と比較して待遇が低くなっている企業も見られますので、採用されてからの給与や福利厚生などが充実していない可能性がでてきます。
短期間に転職を繰り返すのは避けたほうが無難
短期間に転職を繰り返すと、採用担当者に与える不安がさらに大きくなってしまいます。
そもそも第二新卒の場合は、会社に長く務めた実績がないため、短い期間の就業が多いと採用する側としても不安を感じずにいられない状況になるわけです。
したがって、これといった理由もなく短期間に転職を繰り返すのはデメリットが大きくなるため、注意をしましょう。
転職回数は企業側も気にしている
第二新卒を採用する際には、企業側でも転職の回数や勤続年数は念を入れてチェックしています。
ニーズが高いとはいえ、やはり転職回数が多い、勤続年数が短いといった場合は、企業側も採用する際にためらいが生じるようです。
転職回数が3回を超えている
ある調査データでは、応募者の転職回数が3回を超えている場合、約35パーセントの企業が「気になる」と回答しているという結果が出ています。
ただ、転職の回数が4回の場合は約30パーセント、5回の場合は約19パーセントの企業が「気になる」と回答していますので、転職の回数が多いからと言って、必ずしも不利になるとは言えないようです。
前職を1年以内に辞めている
ちなみに、前の仕事を1年以内に辞めている応募者に対して、「気になる」と答えた企業は約70パーセントです。
このように短期間の就業の場合は、半数以上の企業が気になると回答していることが分かります。
不利になるかどうかは業種によって多少変わることも
エンジニアやデザイナーといった職種に応募するときには、とくに職務経歴の書き方を工夫する必要があります。この手の技術系の仕事は、ブランクの期間があることが、1つのデメリットになります。
ブランクがある分だけスキルが磨かれていないと判断されてしまうと、採用の合否にも響いてくるでしょう。
中小企業やベンチャー企業は狙い目

第二新卒といっても、その捉え方は企業によって異なる場合があります。
一般的には「社会人経験がおおむね3年程度」というのが第二新卒の定義になっていますが、こういった定義に当てはまらない人材を第二新卒として採用している企業も中には見られます。
例えば、中小企業やベンチャー企業では第二新卒の定義が少し異なることがあります。
社会人経験が5年以上であっても、第二新卒者として受け入れている場合があります。
第二新卒は、中小企業やベンチャー企業からはおおむね人気が高く、働き始めてから5年前後経っている人材も積極的に採用しているケースがあります。
今後、自社で活躍してくれそうな人材であれば、ある程度の年齢に達していても第二新卒として受け入れてもらえる可能性があるわけです。
したがって、応募する企業によっては、年齢や学校を卒業してからの期間、就業期間などにこだわりすぎることはないでしょう。
転職を取り巻く環境の変化
2018年に起こったリーマンショックの影響が落ち着いた2010年以降は、求人倍率が大きく上昇しています。
平成30年の1月には、日本の有効求人倍率は1.59倍になり、転職活動がしやすくなっています。
東京都の場合は、有効求人倍率は2.08倍まで上昇していますので、これから転職する人にとっては、非常に有利な環境と言えるでしょう。
第二新卒などの若い人材のニーズが高くなった
リーマンショックの影響を受けていた不況の時期には、企業も新入社員の採用を控えるケースが目立ちます。
このようなスタイルを続けていると、社内に若い社員が少なくなる、などの問題が生じてきます。
経済状況が回復の兆しを見せてからは、若手の人材を積極的に採用する企業が増えてきました。
20代の第二新卒者や既卒者などは、とくにニーズが高まっている状況です。
人出不足の問題を抱える企業が増えた
経済状況が回復して業績が上がってくると、社内の仕事も増えるのが常。
支店や支社を設けるなど、業務の拡大をする企業も見られるようになり、人出不足の問題が深刻化しています。
団塊の世代が退職の時期を迎え始め、企業を支える若手の人材が求められています。
求人が多くなる時期がチャンス
転職を成功させるためには、求人が多い時期を狙って活動をしたほうが有利です。
第二新卒の場合も、求人が多くなる時期というものがありますので、タイミングを逃さないようにしましょう。
人材の入れ替えの時期に合わせて入社してほしいというのが企業の希望であり、人事異動が増える時期はとくに狙い目です。
新年度を控えた1月から3月
4月は、多くの企業が新しいスタッフを迎えて業務をスタートします。
春先には人事異動が行われることも多く、社内のメンバーが一新する時期でもあります。
このような4月を控えた1月から3月は、一般的に求人が増える時期です。
新メンバーの1人としてほかの社員と一緒に活躍してほしいということで、第二新卒者の採用を積極的に行う企業が増えてきます。
異動が多い10月を控えた7月から9月
一部の企業では、10月にも人事異動などが行われています。
こういった時期に先駆け、7月から9月ごろに新入社員の採用活動をスタートする企業も少なくありません。
優秀な第二新卒を確保したい企業の中には、あえて新年度の春を避けて秋に採用を行うケースもあります。
第二新卒者が面接で心掛けたい事
第二新卒者の面接にあたっては、新卒就活者とは違う対策を練る必要があります。
「無事に書類選考が通ってせっかく面接までたどり着いたのに、対策を練っておかなかったばかりに落とされてしまった」ということになっては、時間のロスになるだけではなく、精神的にも大きなダメージを負いかねません。
ここでは、第二新卒者が面接で気を付けたいポイントについて解説します。
ひとつひとつ目を通していきましょう!
転職理由の伝え方には要注意!
第二新卒者が面接を受ける上でまず気を付けたいのが、「転職理由の伝え方」についてです。
転職を決意した理由は人さまざまですが、「休日出勤が多くて嫌になった」「想像していた仕事と違ってがっかりした」などと、何の工夫もせずにそのまま伝えてしまう事は厳禁です!
仕事に対する意欲を疑われてしまうばかりか、「退職するのを会社のせいにしている」と思われてしまう恐れさえあります。
「業務に携わる中で、他の会社で働く方が自分の能力がより発揮できると感じました」
という具合に、転職理由を伝える際にはうまく言葉を選びましょう!
自己PRは正直に熱く!
転職を成功させたいあまり、身の丈以上の能力をアピールすることは厳禁です!
もし企業がその能力に期待して採用を決めた場合、自分の能力以上の仕事を任されてしまう事があります。
その結果、処理しきれない仕事にストレスを感じ、再び転職を考えるという事にもなりかねません。
自己アピールをする上では、「今の自分の能力をどのように応募先の企業で発揮していくか」と言うことを意識しましょう。
もちろん、採用後には新たな能力やスキルを習得していく姿勢を厚くアピールすることも大切です!
応募書類は充実したものにしよう!
企業によっては、面接の前に書類選考を設けている場合も多いです。
そういった企業の場合、応募者の第一印象は当然応募書類によっておおよそ決定してしまいます。
そのため、応募書類が手抜きのものであったり熱意が伝わらない内容であった場合、面接にこぎつける事は非常に困難でしょう。
応募書類で特に重要な部分は、「志望動機」と「自己PR」です。
企業のニーズと合致するような自己PRや、熱意が伝わるような志望動機を作成しましょう。
もちろん、誤字や脱字が無いかチェックすることもお忘れなく!
応募書類の作成に自信がない場合は、後程紹介する転職エージェントに相談するのも手ですよ!
全体的な転職のスケジュールを把握しておく

転職活動をするうえでも、スケジュール管理を徹底することが重要です。
自己分析や情報収集にどのくらいの時間がかかるか、また、応募から選考までに要する期間などを考えたうえで、スケジュールを組む必要があるでしょう。
内定獲得までは、数カ月から半年程度かかる
自己分析から転職活動をスタートすると、実際に応募をして内定を獲得するまで数カ月から半年程度はかかります。
したがって、首尾よく転職を成功させるためには、離職をする半年ほど前から準備をしておくのがベストです。
求人が増えるタイミングなども考えながら、活動を始めましょう。
最初の1カ月から2カ月は転職の準備にあてる
自己分析や企業研究などの情報収集は、応募をする前にぜひ行っておきたい準備です。
最初の1カ月から2カ月の間は、このような準備を行うと順序よく転職活動ができます。
応募から選考、内定までは約1カ月から2カ月
求人に応募をしてから結果が出るまでは、大体1カ月から2カ月といったところです。
企業によって採用スケジュールが変わることもありますので、少しゆとりを持ってスケジュールを考えておきたいところです。
内定を獲得してからも、業務の引き継ぎなどがありますので、実際に勤務先を退職するまでには、1カ月から2カ月程度はかかることが多いです。
自己分析は時間をかけて行う
第二新卒の場合は、前職と違う業種や職種も比較的選びやすいです。
実務経験が少ない分、前職にとらわれることなく自由に仕事を選んでいけます。
選択の幅が広いからこそ、しっかりとした自己分析を行う必要があるでしょう。
自己分析をする際には、転職サイトの自己分析サービスや転職エージェントのキャリアカウンセリングサービスを利用すると便利です。
「リクナビNEXT」などの転職サイトには、「グッドポイント診断」を始めとする気軽に利用できる自己分析のサービスがあります。
また、「DODA」などの転職エージェントのキャリアカウンセリングも、自己分析には役立つでしょう。
実のところ、将来のキャリアプランも含めた自己分析のために、時間や手間を惜しむべきではありません。
利用しやすいサービスを見つけて、自分の長所やアピールポイントなどを把握してみましょう。
リクナビNEXTの口コミ・評判は悪い?サービス内容や利用の流れも解説!
転職先が決まるまでは退職をしない
転職活動を進める際には、相応の支出が発生します。
万が一転職先が決まる前に退職をしてしまうと、金銭的な余裕を失った状態で転職活動を行わなければならなくなるのが問題です。
経済的、精神的に追い詰められると、自己分析や転職先の選び方などで失敗する可能性が高いため、退職をするタイミングには気を付ける必要があります。
多忙な状況でも、転職先が決まるまではできるだけ退職をしないのがベストです。
また、転職活動のスケジュールを正確に把握しておくことも重要になるでしょう。
スケジュールを読み違えてしまうと、退職の申し出などを早々に済ませてしまう可能性もでてきます。
面接などで、採用担当者から内定をほのめかすようなコメントがあった場合でも、実際に結果が出るまでは思いのほか時間がかかることもあります。
腰を据えて転職活動に取り組むことが大切
日本経済の影響もあり、第二新卒は企業側からのニーズが高まっています。
したがって、求人を探すときや応募をする際にむやみに焦ったり慌てたりする必要はありません。
精神的に焦りが生じると、判断力が狂うこともあります。
ブラック企業などに引っかかってしまう可能性もでてきますので、要注意です。
希望に適う結果を得るためには、転職の準備などにじっくりと時間をかけて取り組むことが大切になるでしょう。
自己分析を始め、企業の風土や職場の雰囲気なども調べておくと、仕事を始めてからも役立つことが多いです。
転職サイトや転職エージェントなどのサービスを利用するのも、1つの方法になるかもしれません。
後悔のない選択をするためには、じっくりと腰を据えて転職活動に取り組むのがおすすめです。
スケジュールをしっかりと立てておけば、理想的なペースで新しい仕事を始められるでしょう。
譲れない条件を設定しよう
第二新卒者の転職活動で重要なポイントの一つとして、「譲れない条件を設定する」と言うことも忘れてはいけません。
上で述べた通り、第二新卒者が転職活動をする上では、腰を据えてどっしりと構えることが重要です。
そのためには、必ず転職先に望む譲れない条件をいくつか設定することが大切です。
というのも、こうした条件を設定しておくことで、転職活動がうまくいかない焦りから妥協の結果理想とは程遠い職場に転職してしまうことへのブレーキとなるからです。
とはいえ、度を超えた好条件を設定するのは厳禁です!
理想と現実との折り合いをうまくつけながら、譲れない条件を設定しましょうね!
企業のニーズもチェックしよう
転職活動で大切なこととして、「自分が転職先の企業のニーズに沿っているか」を考えるという事が挙げられます。
どんなに自分が働きたい企業が見つかったとしても、自分が企業のニーズとかけ離れている場合には転職は難しいでしょう。
いくら興味のある求人でも、あまりにも自分が企業のニーズとかけ離れている場合、たとえ応募したとしても徒労に終わってしまいかねません。
ただしどうしても諦めきれない場合には、思い切って応募をしてみるのも一つの手です。
熱意が企業に伝われば成長意欲を評価してもらえる場合もありますよ!
第二新卒の転職成功には転職エージェントを活用しよう!
第二新卒者の転職活動に不可欠なものに「転職エージェント」があります。
自分一人で行う転職活動は時間的にも体力的にも限界がありますよね。
以下に、オススメの転職エージェントを紹介します。
ぜひ活用しましょう!
doda

| 求人数 | 約260,000件 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国47都道府県 |
| 料金 | 無料 |
| 公式サイト | https://doda.jp/ |
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
オススメの転職エージェント一つ目が、こちらの「doda」です!
求人数も豊富で、腕利きのエージェントが希望の条件などを丁寧にヒアリングしてくれますよ!
ハタラクティブ
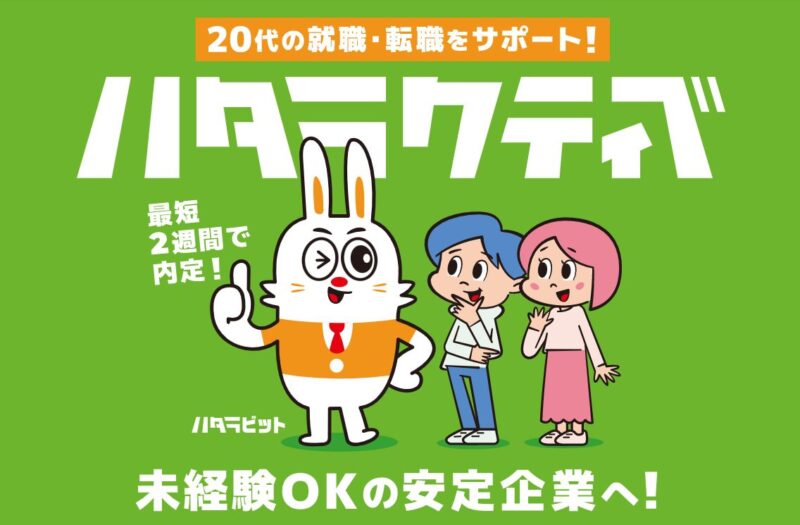
ハタラクティブの特徴
- 経歴に自信がなくても転職成功できる
- アドバイザーのサポートが手厚い
- LINEでのカウンセリングが可能
オススメの転職エージェント二つ目が、こちらの「ハタラクティブ」です!
20代の転職に特に強く、職歴や学歴などの経歴に自信がない人に特におすすめです!
マイナビエージェント

マイナビエージェントの特徴
- キャリアアドバイザーが丁寧にサポートしてくれる
- 非公開求人が多い
- サービスが充実している
- 20代など若者の転職に強い
オススメの転職エージェント三つ目が、こちらの「マイナビエージェント」です!
若者の転職に強いことが特徴で、面接対策や応募書類の添削なども丁寧に指導してくれます!